
-刑事事件の各段階で目指すゴール-
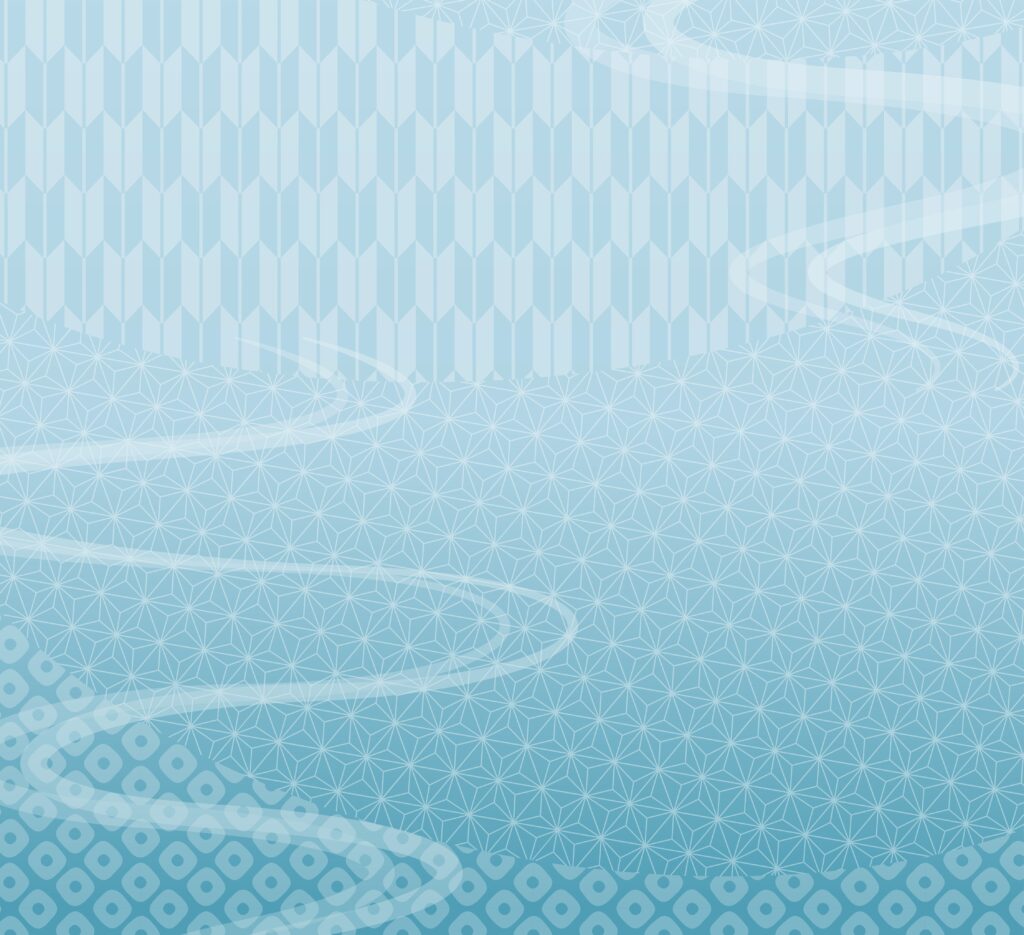
目次
0 刑事弁護における獲得目標
1 逮捕を回避する
2 身体拘束を回避する(被疑者勾留)
3 身体拘束からの解放(被疑者勾留)
4 不起訴処分を獲得する
5 身体拘束からの解放(被告人勾留)
6 執行猶予付判決を獲得する
7 実刑判決の刑期を軽減する
8 無罪判決を獲得する
9 結語
0 刑事弁護における獲得目標
刑事事件において、弁護人をつける意味は、被疑者・被告人にとって少しでもメリットになる結果を実現することにあります。最終目標としては、犯罪事実の存在自体を否定する否認事件では無罪の獲得、犯罪事実自体は認めたうえで反省を示す自白事件では執行猶予判決の獲得ですが、その段階に至る前にも獲得目標があります。
刑事事件は、以下のとおり、いくつかの段階を経て進行する手続です。犯罪の種類や被疑者・被告人に関する具体的事情により、現実的に獲得が可能なものと、獲得が難しいものに分かれますが、私選刑事弁護は、実際の事案に照らして、獲得しうる目標をなるべく手続の手前の方からひとつずつ獲得する活動を行います。
ここでは、私選刑事弁護において、被疑者・被告人のために獲得を目指すべき目標について、解説します。
【刑事事件の流れ図・身柄事件】
- 犯罪の発生・捜査の開始
- 警察による逮捕・取調べ
- 警察から検察への送致(送検)・検察の取調べ・勾留請求
- 裁判官の勾留質問・勾留決定
- 被疑者勾留の開始・勾留延長
- 検察官による処分(起訴・略式起訴・不起訴)
- 被告人勾留
- 公判
- 判決
1 逮捕を回避する
事件が発生し、捜査機関による捜査が開始された後、最初に発生する不利益が「逮捕されるか否か」です。捜査が開始されると逮捕されるという印象を抱く方も多いですが、必ずしもそういうわけではありません。この段階では、逮捕された状態で刑事手続が進行する「身柄事件」と、通常の社会生活を続けながら警察の呼び出しに応じる形で刑事手続が進行する「在宅事件」に振り分けられます。
逮捕は、①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、②逮捕の必要性(「逃亡するおそれ」「罪証を隠滅するおそれ」)が認められる場合に可能となります。逮捕により身体が警察の留置施設に入ることになりますので、たとえプライベートの場面の行為を理由とする逮捕であっても、家族または職場や学校に逮捕の事実が知られる可能性が高まります。また、逮捕をきっかけに各種報道機関に報道されることもあり得ます。
逮捕を回避するための活動として、【警察への意見書の提出】があります。意見書の中で、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説明し、身柄引受人の確保ができれば、警察が逮捕せずに在宅事件で進行する判断をすることもあります。その場合は、逮捕後、勾留される前に釈放となります。
しかし、実務上、逃亡や罪証隠滅のおそれはとても広範に認められており、事態発生の「可能性」を否定しきれない限りは、「おそれ」があると判断されることが多く、また、逮捕の場面では、後述する被疑者勾留とは異なり、逮捕に対する不服申立てが認められておらず、令状という制約はあるものの事実上警察の判断のみで逮捕が可能となるため、警察が自身の判断を覆して逮捕しないと判断するのはハードルが高いというのが実情です。
また、一般的に重大犯罪など重い刑罰が予想される場合、共犯者がいる場合、罪を認めていない場合などは、それ自体で逃亡・罪証隠滅のおそれが認められるとして、逮捕を免れることができないことがあります。
なお、犯罪の事実を捜査機関が認識する前であれば、【自首】をすることができます。自首は、自ら犯罪事実を認めて処分を求める行為であるため、逃亡・罪証隠滅のおそれを薄める性格を有しています。犯罪の種類にもよりますが、逮捕回避の有効打になる可能性が高いといえます。
2 身体拘束を回避する(被疑者勾留)
逮捕された後、被疑者が警察から送検され、検察官が勾留(逮捕に引き続いて行われる身体拘束)の必要があると判断すると裁判所に対して勾留請求が行われます。勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対して勾留質問を行い、勾留すべきと判断した場合は、勾留決定を行います。この勾留決定により、被疑者は10日の被疑者勾留を受け、その後に勾留延長があれば最大10日の被疑者勾留が追加で付されることになります。
この段階の弁護活動は、「勾留をつけさせない」ことです。勾留請求をする検察官には【勾留請求に対する意見書】、勾留決定をする裁判官には【勾留に対する意見書】を提出します。いずれも、被疑者を勾留するための要件を満たしていないこと、具体的には、①勾留の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由、住居不定、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由、逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当な理由)がないこと、②勾留の必要性がないことを強く訴えることになります。
上記のうち、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」は、証拠書類や証拠物を物理的に破棄隠匿する行為だけでなく、被害者や関係者への接触を含むものであるため、検察官及び裁判官はこの点を容易に認めてしまうのが実状です。一方で、後述する裁判官が行った勾留決定を事後的に覆す準抗告とは異なり、そもそも勾留をつけるか否かの場面であるため、柔軟な対応を期待できる側面もあります。国選弁護人は、勾留決定後に選任されるため、この場面で勾留を争うことができるのは私選弁護人のみであり、検察官または裁判官と粘り強く交渉をすることになります。
3 身体拘束からの解放(被疑者勾留)
裁判官の勾留決定により、被疑者勾留が開始した場合、最初は10日間、勾留延長の請求により追加で最大10日間は身体拘束を受けることになります。具体的な事案にもよりますが、基本的には勾留延長となることが多いため、20日間の勾留期間と考えて行動した方が無難でしょう。
この段階の弁護活動は、1日でも早く「身体拘束を解く」ことです。具体的には、裁判官が行った【勾留決定に対する準抗告】や、【勾留取消請求】、勾留延長された場合の【勾留延長に対する準抗告】となります。それぞれ、認容される要件は若干異なりますが、裁判所が判断する際の分水嶺となるのは、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由の有無、逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無であることがほとんどです。
既述のとおり、実務上はこの2点について、被疑者にとって厳しい判断になることが多いというのが実情ですが、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを裏付けとなる資料と合わせて丁寧に訴えることや、【被害者との示談】が成立した等の追加の事情により、認容されることがありますので、積極的にトライする姿勢が重要となります。
4 不起訴処分を獲得する
被疑者勾留の最後に検察官が処分をすることになります。検察官の処分は、起訴(公判請求)、略式起訴、不起訴のいずれかです。不起訴処分になると、刑事手続は公判に進むことなくこの段階で終了し、身体拘束が終了し、前科もつかないため、被疑者にとっては有利な結果となります。
不起訴には、主に①嫌疑なしの不起訴、②嫌疑不十分の不起訴、③起訴猶予の不起訴(犯罪事実はあるものの諸般の事情を考慮し、検察官の判断で起訴をしない)があります。
この段階の弁護活動は、実際に判断を行う検察官に対して、【不起訴処分を求める意見書】を提出することです。嫌疑なしあるいは嫌疑不十分の事情がある場合は、具体的な事実関係や証拠に言及しつつ犯罪の嫌疑に関する論証を行います。起訴猶予の場合は、被疑者を起訴すべきではない被疑者にとって有利な事情を裏付けとなる資料とともに説得的に論じることになります。起訴猶予については、諸般の事情を考慮のうえ、積極的に起訴しないという判断をするものですので、その理由(大義)にふさわしい事情を情報として提供することで、不起訴処分獲得の可能性を上げることができます。
5 身体拘束からの解放(被告人勾留)
起訴によって、従前の被疑者勾留は被告人勾留に切り替わります。被告人勾留においては、身体拘束を解くための【保釈請求】が認められております。保釈は、保釈保証金の納付を条件として、被告人の身体を警察署の留置施設や拘置所から釈放し、社会内で生活する状態で公判期日を向かえることができる仕組みです。
保釈のためには、保釈請求が裁判所に認められ(逃亡・罪証隠滅を疑うに足りる相当の理由がない、保釈の必要性がある等の条件のほか、身元保証人が必要となります)、裁判所が定めた保釈保証金の納付を済ませる必要があります。保釈保証金は、被告人の個別事情や犯罪の種類によって定められますが、150万円から300万程度が一般的な相場となります。基本的には家族等が用意することになりますが、日本保釈支援協会による保釈保証金の立替を利用することもできます。保釈保証金は、被告人が逃亡することなく、公判期日に出頭し、判決を受けるのであれば、全額返金されます。
この段階の弁護活動は、「裁判所に保釈請求を認めてもらう」ことです。保釈請求が却下された場合は、準抗告(不服申立て)で対抗したり、再度の保釈請求をしたりと粘り強い対応が必要となります。保釈請求においても、逃亡と罪証隠滅を疑うに足りる相当の理由が要素となりますが、保釈の場合は保釈保証金によりある程度は逃亡の危険性を薄めることができるため、罪証隠滅の部分を念入りに手当する必要があります。身体拘束がいつまで続くかという問題になるため、なるべく早めに釈放を目指したいところですが、犯罪の種類や被告人の個別事情によっては保釈が認められにくいことがあるのも事実です。公判期日後判決までの期間については、罪証隠滅の可能性は限りなくゼロになるため、釈放後の期間は最短になるものの効果的な保釈請求を期待することができます。
6 執行猶予付判決を獲得する
起訴された後に実施される公判において、公訴事実にかかる審理が行われ、裁判所の判決が示されます。判決は、重い順に①実刑判決、②執行猶予付の実刑判決(保護観察付執行猶予を含む)、③無罪判決のいずれかです。
公訴事実の存在を争わない場合は、実刑判決か執行猶予付判決のどちらかになるため、判決後に刑の執行が始まる実刑判決よりも、一定の期間、刑の執行を猶予し、猶予された期間中に新たな犯罪を重ねなければ刑の言渡しの効力が失われる執行猶予付判決の方が有利となります。執行猶予付判決の場合、判決直後に刑務所に収監されることなく、社会内で通常の生活をすることができるため、前科は残るものの、被告人が受ける不利益を最小限に抑えることになります。
執行猶予判決を得るためには、公判の場面において、犯情事実(犯罪に至る経緯、動機、目的、計画性、犯行態様、結果など)と一般情状事実(生い立ち、年齢、前科前歴、反省、示談・被害弁償など)の両面から重い処罰をすべきではないことを丁寧に説明し、裁判所を説得する必要があります。弁護人は、公判手続内の【弁護側立証(書証、証拠物、証人尋問、被告人質問)】と【弁論】の段階で、被告人に対して重い処罰(実刑)をすることが適切でないことを、強く訴えます。
7 実刑判決の刑期を軽減する
執行猶予付判決をするためには一定の条件があります。刑の全部執行猶予(刑法第25条)の場合は、(1)①前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者、または、前に拘禁刑以上の刑に処されたことがあってもその執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者が、②3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、③情状により裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の執行を猶予することができる。(2)①前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、②情状に特に酌量すべきものがあるときは、③裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。当該条件を満たすことができない場合は、そもそも執行猶予付判決を得ることができません。
執行猶予付判決を獲得できない以上、次に獲得目標とするのは、拘禁刑の刑期を少しでも削ることです。刑期の短縮により、社会復帰の時期が早まることになりますので、被告人の受ける不利益を最小限にとどめるために重要な弁護活動となります。
刑事裁判の構造上、訴追をする検察官は、被告人にとって厳しい判決を求めることになるため、検察官立証でも被告人に不利な事情を主張されることになります。裁判官は職業上、バランス感覚に優れておりますが、判断の基礎となる情報が被告人にとって不利な事情であふれていると厳しい判決に心証が傾いてしまうことになります。そのため、弁護人としては、裁判官が事案について、バランスのよい判断ができるよう、公判において被告人にとって有利な事情を強く訴えることになります。犯情事実と一般情状事実の両面から有利な要素を主張する点は執行猶予付判決を狙う場合と変わりません。
8 無罪判決を獲得する
犯罪事実の存在を否定する否認事件の場合、無罪の獲得を目指すことになります。無罪獲得のためには、捜査機関側に積極的に証拠を与えないために捜査段階の取調べで黙秘を貫くなどの対応が必要となりますので、刑事手続の初期の段階から戦略的に進める必要があります。また、「推定無罪の原則」はありますが、残念なことに、否認で刑事手続を進めると、逮捕や勾留となる可能性が高く、身柄拘束からの解放も難しくなるという現実がありますので、無罪主張には相当な覚悟が必要です。
実際に身に覚えがないえん罪であるならば、当然、徹底的に戦って無罪を目指すべきです。一方で、実際は犯罪行為を行ったもののなんとなく無罪を主張したいという考えであれば、あらゆる場面で不利益が発生するリスクもあるため、慎重に判断した方がよいといえるでしょう。
9 結語
以上が刑事弁護において獲得を目指す手続段階別の目標となります。基本的には、手続の手前側(捜査開始・逮捕)から実現を狙うことになりますが、手続の進行度合いによっては、そもそも対応が間に合わないという事態も想定されます。特に、逮捕の回避、身体拘束の回避(被疑者勾留)は、1日単位で被疑者の置かれた状況が大きく変わり、弁護人の接見や準備のための時間を考慮すると、時間的な余裕はほとんどない状態です。そのため、言葉どおり「一刻も早く」弁護士へ相談することが、被疑者のその後の運命を大きく左右することになるといえるでしょう。
検察の不起訴処分や裁判所の判決(執行猶予、実刑の刑期短縮)に関しては、ある程度、備えるための時間を確保することができますが、準備のほかに「有利な事情」を集めるための時間(たとえば、被害者との示談)が必要となることを考えると、なるべく早い段階で弁護士が関与できていることが被疑者・被告人にとっての最善の選択です。特に国選弁護人から私選弁護人に切り替えるという場合、決断したならばなるべく速やかに私選弁護人を選任し、後任の弁護人で使える時間を十分に確保することが、被疑者・被告人にとっておおきなメリットにつながります。
刑事事件は、時間が限られたタイトな手続であって(一般的な例だと、逮捕から勾留まで3日間、被疑者勾留が20日間、起訴から公判までが1ヶ月半から2ヶ月程度、公判から判決までが1週間から10日程度)、その速度感は民事事件や家事事件(事案によって1年を超えることも多い)と比べものにならないほど速いといえます。そのため、その瞬間瞬間の判断が最終的な結果に直結する極めて重要なものとなります。前科がつくつかない、刑務所にいくいかない、有罪か無罪か、いずれもが被疑者・被告人の人生に大きな影響を与えることになりますので、万全を期すためにも、弁護士への相談をご検討された方がよいでしょう。